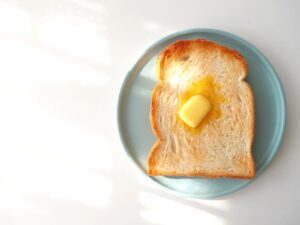
2025.10.10
ごはんの味が変わる。お米の選び方・保存・炊き方で差がつくポイント
調理と保存のコツ

炊き立てのごはんを口に運んだ瞬間、「あれ、なんだか味が落ちた?」と感じたことはありませんか。同じ炊飯器、同じ水加減なのに、どこか物足りない。そんな経験をされた方は少なくないと思います。
実は、お米の美味しさは炊飯器の性能や炊き方だけで決まるわけではありません。どのお米を選ぶか、どう保存するか、そして炊く前のひと手間──この3つを整えるだけで、普段のごはんが驚くほど変わります。
ここでは、毎日の食卓で「ちょっといいごはん」を食べるために知っておきたい、お米の基本と実践的なコツをまとめました。
なぜ同じお米でも味が変わるのか
お米は生鮮食品に近い性質を持っています。精米した瞬間から、空気中の酸素や湿気に触れることで少しずつ酸化が進み、風味が落ちていきます。
たとえるなら、りんごを切った断面が茶色くなるのと同じ仕組みです。表面のぬか層が取り除かれた精白米は、酸化のスピードが速くなります。
また、保存環境によっても味は大きく左右されます。高温多湿の場所に置いておくと、カビや虫が発生しやすくなるだけでなく、お米自体の水分バランスが崩れて、炊き上がりがベタついたり、パサついたりする原因になります。
つまり、お米の美味しさを守るには「鮮度」と「保存環境」の両方を意識することが大切です。
お米の選び方で押さえておきたいこと
精米日は「2週間以内」を目安に
スーパーで「新米」と書かれたお米を見かけると、つい手が伸びますよね。でも実は、新米表示よりも大切なのが精米日です。
精米してから時間が経つほど、風味は落ちていきます。できれば精米日から2週間以内のものを選ぶのがおすすめ。1〜2か月で食べ切れる量を小分けで購入するほうが、まとめ買いよりも結果的に美味しく食べられます。
新米は水加減を調整する
秋に出回る新米は、収穫してから間もないため水分量が多めです。普段通りの水加減で炊くと、やわらかすぎる仕上がりになりがち。水を1割ほど減らすだけで、粒立ちの良いごはんに変わります。
古米が余ったときの活用法
一方、前年度産の古米が残ってしまった場合は、新米とブレンドしてみてください。水分量のバランスが調整され、炊き上がりが安定します。
また、古米を炊くときに酒やみりんを小さじ1ほど加えると、ツヤと香りが戻りやすくなります。捨てずに工夫して使い切ることで、食品ロスも減らせます。
保存の工夫で美味しさを守る
野菜室+密閉容器がベスト
精米後のお米は、温度と湿度が安定した場所で保管するのが理想です。おすすめは冷蔵庫の野菜室に密閉容器で保存すること。
野菜室は温度が10℃前後、湿度も適度に保たれているため、お米の鮮度を長持ちさせやすい環境です。さらに密閉することで、冷蔵庫内のにおい移りも防げます。
虫よけには乾燥とうがらしやローリエを
米びつに入れておく虫よけとして、昔ながらの乾燥とうがらしが有名ですが、ローリエの葉も効果的です。虫が嫌がる香り成分が含まれており、開けたときに爽やかな香りがするのもうれしいポイントです。
炊いたごはんは冷凍保存がおすすめ
余ったごはんは冷蔵庫に入れがちですが、実は冷蔵保存するとデンプンが劣化し、硬くてパサパサした食感になってしまいます。
小分けにしてラップで包み、冷凍保存するのがベスト。電子レンジで解凍すれば、炊きたてに近いふっくらした食感を楽しめます。
炊き方のひと工夫で甘みを引き出す
浸水時に氷を入れる
お米の甘みを引き出したいときに試してほしいのが、浸水時に氷を入れる方法です。
水温がゆっくり上がることで、お米のデンプンが糖に変わる「糖化」が進みやすくなり、甘みが際立ちます。氷を入れた分だけ水を減らすのがコツ。手軽にできる割に効果を感じやすい方法です。
古米には昆布をひとかけ
風味が落ちた古米を炊くときは、昆布をひとかけ入れるのもおすすめ。昆布のグルタミン酸がごはんに移り、旨味が加わります。シンプルな白ごはんでも、どこかごちそう感が出るのが不思議です。
無洗米の特徴と上手な使い方
「とがずに炊ける」無洗米は、忙しい日常の味方です。表面のぬか層があらかじめ取り除かれているため、水質に左右されにくく、におい移りも少ないのが特徴。夏場やアウトドアシーンでも扱いやすいお米です。
ただし、炊き方には少しコツがあります。精米時に表面が削れている分、水はやや多めにするのがポイント。通常の精白米と同じ水加減だと、硬めに仕上がることがあります。
品種の違いを楽しむ
お米は品種によって、甘み、粘り、食感がまったく異なります。料理や好みに合わせて選ぶと、食卓がもっと楽しくなります。
◎コシヒカリ
甘みと粘りが強く、冷めても美味しいのが特徴。お弁当やおにぎりに向いています。
◎あきたこまち
ややあっさりした味わいで、和食全般によく合います。粘りと硬さのバランスが良く、毎日食べても飽きにくい品種です。
◎ササニシキ
粘りが少なくさらっとした口当たり。寿司や丼ものなど、具材の味を引き立てたい料理にぴったりです。
◎ゆめぴりか
もちもちとした食感と強い甘みが特徴。洋食や濃い味付けの料理にも負けない存在感があります。
どれが正解というわけではありません。いろいろ試して、自分や家族の好みに合う品種を見つけてみてください。
いつものごはんを、もう少し美味しく
お米は、日本人にとって最も身近な食材のひとつです。だからこそ、「どれも同じ」と思いがちですが、選び方・保存・炊き方を少し意識するだけで、味は大きく変わります。
高級なお米を買わなくても、特別な調理器具がなくても、今日からできることはたくさんあります。
まずは、次にお米を買うとき、精米日を確認するところから始めてみませんか。その小さな一歩が、明日の朝の一膳を、ちょっと特別なものにしてくれるはずです。
ご相談・依頼はこちら
まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
管理栄養士・料理家
ひろのさおり
お茶の水女子大学大学院在学中、フリーランスとして管理栄養士のキャリアをスタート。レシピ開発や執筆業、出張料理サービスに携わり、特定保健指導、セミナー・料理教室講師としても活動を広げる。現在は株式会社セイボリーの代表を務め、レシピ開発・料理撮影や、調理器具や食品の監修・販促サポートなどの事業を営む。テレビ出演などのメディア実績も多数。著書に「小鍋のレシピ 最新版」(辰巳出版)。









