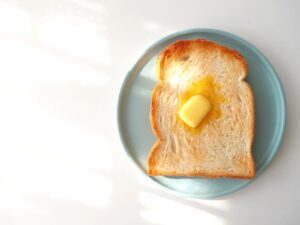
2025.10.01
混ぜ方・組み合わせで変わる。納豆の栄養をムダにしない食べ方
調理と保存のコツ

朝ごはんに納豆を一パック。手軽で栄養もあるから、毎日の習慣にしている方も多いのではないでしょうか。
実は、同じ納豆でも混ぜ方や組み合わせる食材、加熱するかどうかで、体への届き方が変わってきます。ほんの少しの工夫で、栄養の活かされ方がぐっと高まるのです。
せっかく毎日食べるなら、その力をムダなく引き出したいですよね。ここでは、管理栄養士の視点から、納豆の栄養を最大限に活かすコツをお伝えします。
納豆が健康食として愛される理由
納豆は、日本が世界に誇る発酵食品です。大豆を納豆菌で発酵させることで、もともと栄養豊富な大豆の力がさらにパワーアップしています。
まず注目したいのがビタミンK。骨の健康を守り、血液の凝固にも関わる大切な栄養素です。とくに骨粗しょう症が気になる方や、成長期のお子さんにとっては見逃せません。
次にビタミンB1。糖質をエネルギーに変える働きがあり、疲れやすい方や、ごはんやパンをよく食べる方には欠かせない存在です。
そして、納豆菌が生み出すナットウキナーゼ。血液の流れをサラサラに保つ働きがあるとされ、生活習慣が気になる世代から注目を集めています。
さらに、良質なたんぱく質、腸内環境を整える食物繊維、体の調子を整えるミネラルまで。小さなパックの中に、健康を支える成分がぎゅっと詰まっているのです。
ただし、同じ納豆でも「どの種類を選ぶか」「どう食べるか」で、その栄養の活かされ方は変わってきます。
粒とひきわり、選び方で変わる栄養バランス
スーパーの納豆売り場には、「粒」と「ひきわり」が並んでいますよね。見た目の違いだけと思われがちですが、実は栄養バランスにも特徴があります。
ひきわり納豆は、大豆を細かく刻んでから発酵させるため、納豆菌が触れる面積が広くなります。その結果、ビタミンKの含有量が多いのが特徴です。骨の健康が気になる方、血液の凝固に関わる栄養を効率よくとりたい方には、ひきわりがおすすめです。
一方、粒納豆は大豆の皮が残っているため、食物繊維や鉄、マグネシウムなどのミネラルが豊富。お通じが気になる方や、貧血が気になる女性には粒タイプが向いています。
どちらが優れているというわけではありません。「今日は骨のために」「明日は腸のために」と、目的に合わせて使い分けるのが賢い選び方です。
吸収を高める組み合わせの知恵
納豆は単体でも栄養価が高い食品ですが、一緒に食べる食材によって、その吸収率をさらに高めることができます。
油と一緒にとるとビタミンKの吸収がアップ
ビタミンKは脂溶性ビタミン。つまり、油に溶けることで体に吸収されやすくなる性質を持っています。
ごま油をひとたらし、オリーブオイルを少量かける。たったこれだけで、ビタミンKの吸収率がぐっと高まります。チャーハンや炒めものに加えるのも、理にかなった食べ方です。
「納豆に油?」と驚くかもしれませんが、香ばしい風味が加わって、意外とおいしいですよ。
ねぎや玉ねぎでビタミンB1の働きをサポート
納豆に刻みねぎを添えるのは、味の面だけでなく栄養面でも正解です。
ねぎや玉ねぎ、にんにくに含まれるアリシンという成分は、ビタミンB1と結びついて、その吸収を助ける働きがあります。
糖質をエネルギーに変える力が高まるため、ごはんをしっかり食べる朝や、疲れが気になるときには、納豆+ねぎの組み合わせが理想的です。
日常に取り入れやすいアレンジと食べ方のコツ
納豆はそのまま食べてももちろんおいしいですが、ちょっとした工夫で味わいも栄養価もアップします。
混ぜ方ひとつで変わるおいしさ
「納豆は何回混ぜるのが正解?」という議論を聞いたことがある方も多いでしょう。
実は、30回以上しっかり混ぜると、粘り成分であるポリグルタミン酸が増え、うま味とコクが深まります。空気を含ませるように、ふんわりと混ぜるのがポイントです。
タレは混ぜた後に加えるのがおすすめ。先に入れると粘りが出にくくなります。
香ばしく炒めてアレンジ
ひきわり納豆を油で軽く炒めて、チャーハンや野菜炒めに加えるのもおすすめです。油との相性でビタミンKの吸収率が高まりますし、独特のにおいが苦手な方でも食べやすくなります。
カルシウムと合わせて骨をサポート
粉チーズやしらすをトッピングすれば、ビタミンKとカルシウムの相乗効果で、骨の健康をしっかりサポートできます。ビタミンKには、カルシウムを骨に届ける働きがあるからです。
たんぱく質をプラスして栄養バランスアップ
ツナや卵を加えると、より充実したたんぱく質源に。朝食だけでなく、ランチや夕食のおかずとしても活躍します。
保存と調理で気をつけたいこと
納豆の栄養をムダにしないために、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
保存は冷蔵が基本
納豆は冷蔵保存が基本です。賞味期限内に食べきるのが理想ですが、すぐに食べられない場合は冷凍保存も可能です。
冷凍した納豆は、自然解凍してから混ぜて食べましょう。電子レンジで急速に解凍すると、食感が損なわれることがあります。
風味が落ちたときの活用法
開封時にアンモニア臭が強いと感じたら、発酵が進みすぎているサインです。そのまま食べると風味が気になることがありますが、捨てる必要はありません。
チャーハンや炒めもの、お好み焼きなど、加熱調理に回すと、においが和らいでおいしくいただけます。
服薬中の方は医師に相談を
血液をサラサラにする薬(ワーファリンなど)を服用している方は、注意が必要です。
納豆に含まれるビタミンKは、これらの薬の効果を弱めてしまう可能性があります。納豆を食べてよいかどうか、どのくらいの量なら大丈夫か、必ず主治医に確認してください。
自己判断で食べ続けると、治療に影響が出ることがあります。
毎日の一パックを、もっと味方に
納豆は、組み合わせや食べ方を少し意識するだけで、健康をサポートする力がぐっと高まる万能食材です。
粒かひきわりかを目的に合わせて選ぶ。油やねぎと組み合わせて吸収率を上げる。しっかり混ぜてうま味を引き出す。こうした小さな工夫の積み重ねが、体への恩恵を大きくしてくれます。
手軽に食べられるからこそ、「どう食べるか」を少しだけ意識してみませんか。毎日の一パックが、あなたの健康を支える頼もしい味方になります。
参考
- 日本食品標準成分表2020年版(八訂)
ご相談・依頼はこちら
まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
管理栄養士・料理家
ひろのさおり
お茶の水女子大学大学院在学中、フリーランスとして管理栄養士のキャリアをスタート。レシピ開発や執筆業、出張料理サービスに携わり、特定保健指導、セミナー・料理教室講師としても活動を広げる。現在は株式会社セイボリーの代表を務め、レシピ開発・料理撮影や、調理器具や食品の監修・販促サポートなどの事業を営む。テレビ出演などのメディア実績も多数。著書に「小鍋のレシピ 最新版」(辰巳出版)。









