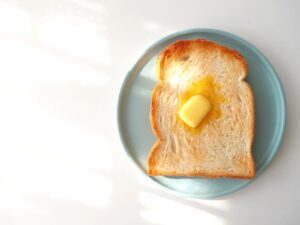
2025.09.16
砂糖の「白」と「茶色」はどう違う?色だけに惑わされない選び方
栄養の基本
調理と保存のコツ

スーパーの砂糖売り場で、ふと立ち止まったことはありませんか。白い上白糖、きび砂糖、黒砂糖、てんさい糖……。パッケージには「ミネラル豊富」「自然派」といった言葉が並び、「茶色い砂糖のほうが体に良さそう」と手が伸びることもあるかもしれません。
でも実は、色の違いがそのまま健康への良し悪しを示しているわけではないのです。
この記事では、砂糖の色が決まる仕組みから、種類ごとの特徴、そして料理に合わせた選び方まで、管理栄養士の視点でやさしく解説します。
砂糖の色はどうやって決まる?
私たちが日常で使う砂糖には、白いものもあれば茶色いものもあります。この色の違いは、栄養価ではなく製造工程や加熱の有無によって決まります。
もともと、砂糖の原料であるサトウキビやてん菜から抽出される糖液は、淡い褐色をしています。そこから不純物や糖蜜(シロップ成分)をどれだけ取り除いたか、また加熱でカラメル化が進んだかによって、見た目や風味が変化するのです。
つまり、白い砂糖は「漂白したから白い」のではなく、高純度の結晶が光を反射して白く見えているだけ。茶色い砂糖は糖蜜が残っていたり、加熱によって色づいたりしているのです。
茶色いから体にいいとは限らない
「茶色い砂糖はミネラルが多くて体に良さそう」というイメージを持つ方は多いですよね。でも実際は、種類によって事情がまったく異なります。
| 砂糖の種類 | 色の理由 | ミネラル含有 |
|---|---|---|
| 白砂糖(グラニュー糖) | 高純度の結晶が光を反射 | 極めて少ない |
| 三温糖 | 加熱によるカラメル化 | 白砂糖とほぼ同じ |
| 黒砂糖 | 糖蜜を分離せず煮詰める | やや多め |
| きび糖 | 糖蜜を一部残す | 微量 |
| てんさい糖 | 原料の色と糖蜜分が残る | ごくわずか |
たとえば三温糖は、白砂糖と同じように高度に精製された糖液を加熱して色づけたもの。見た目は茶色いですが、ミネラル量は白砂糖とほとんど変わりません。
きび砂糖は黒砂糖と同じサトウキビが原料で、風味も似ています。ただ、製造過程で糖蜜の一部を除いているため、黒砂糖ほどの栄養価はありません。
てんさい糖も主成分はショ糖(スクロース)です。まれにオリゴ糖を含む商品もありますが、栄養補給を目的とするなら、豆類や根菜などから摂るほうが効果的です。
つまり、茶色い=栄養があるというイメージは、必ずしも正しくないということ。色だけで判断せず、製法や成分を知っておくと、選ぶ目が変わってきます。
色より大切なのは使い分け
砂糖を選ぶときは、色やイメージにとらわれすぎず、料理の仕上がりや風味に合わせて使い分けるのが賢い方法です。
白砂糖(グラニュー糖)が向いている場面
焼き菓子やメレンゲなど、色をつけずに仕上げたいときに。クセのないすっきりとした甘さで、素材の風味を邪魔しません。シフォンケーキやマカロン、ホイップクリームなど、見た目の白さや透明感を大切にしたいお菓子づくりには欠かせない存在です。
三温糖・きび砂糖・黒砂糖が向いている場面
煮物や照り焼きなど、コクや香ばしさを活かしたい料理に。肉じゃがや角煮に三温糖を使うと、照りと深みが増します。きび砂糖は黒糖ほど風味が強すぎず、家庭料理にも取り入れやすい自然なコクが魅力。黒砂糖は、沖縄料理やかりんとうなど、独特の風味を活かしたいときに向いています。
てんさい糖が向いている場面
素朴な甘さを生かしたい料理やお菓子に。まろやかな甘さは、和菓子やシンプルなおやつ、やさしい味わいに仕上げたいスープや煮込みによく合います。北海道産のてん菜から作られるてんさい糖は、国産原料を選びたい方にも人気があります。
ミネラル補給は食材全体で考える
ミネラルを補いたいときは、砂糖に頼るよりも野菜・海藻・豆類など食材全体のバランスで調整するほうが現実的です。砂糖に含まれるミネラルは、どの種類でも微量。たとえば黒砂糖100gに含まれる鉄分は約4.7mgですが、同じ量を毎日摂るのは現実的ではありませんよね。ひじきやほうれん草、納豆など、日々の食事から少しずつ摂るほうが、無理なく続けられます。
砂糖と健康的に付き合うヒント
砂糖は料理にコクや満足感を加えてくれる、欠かせない調味料のひとつ。ただ、摂り方を間違えると肥満や生活習慣病のリスクが高まる可能性もあります。
色や種類にこだわるよりも、量と使いどころに目を向けることが、日々の健康管理においては大切です。
1日の砂糖摂取目安を意識する
世界保健機関(WHO)が推奨する基準は、1日25g(大さじ約2杯)以内。これは料理や飲み物に使われる砂糖も含めた量です。缶コーヒー1本で10g前後、市販のヨーグルト1個で15g前後の砂糖が含まれていることも。知らず知らずのうちに摂りすぎていないか、少し意識してみるだけでも変化が生まれます。
イメージに惑わされない
「自然派」「茶色い=健康」というイメージだけで選ぶのは避けたいところ。製法や加熱工程による色の違いであり、栄養価に大きな差があるとは限りません。どの砂糖を選んでも、主成分はショ糖。摂りすぎれば体への影響は同じです。
甘い味付けのときは、食事全体でバランスを取る
たとえば、甘辛い主菜を作った日は、副菜をあっさり仕上げる。照り焼きや煮物が続いた翌日は、塩味やだし味のシンプルな料理を選ぶ。こうした全体での調整が、無理なく続けられるコツです。
甘いものを「ゼロ」にする必要はありません。料理の仕上がりを良くしたり、ほっとする一口を楽しんだり。生活にうるおいを与えてくれる甘さと、ほどよい距離感で付き合っていきましょう。
大切なのは色ではなく使い方
砂糖の「白」と「茶色」は、栄養価の差ではなく、製法や加熱による見た目と風味の違いです。どの砂糖も主成分はショ糖であり、健康効果を過信するのは避けたいところ。
重要なのは、量を意識しながら、料理や目的に合わせて使い分けること。
日々の食卓で、必要なときに、必要なだけ。そんなちょうどよい使い方を意識して、砂糖と賢く付き合っていきませんか。
参考
ご相談・依頼はこちら
まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
管理栄養士・料理家
ひろのさおり
お茶の水女子大学大学院在学中、フリーランスとして管理栄養士のキャリアをスタート。レシピ開発や執筆業、出張料理サービスに携わり、特定保健指導、セミナー・料理教室講師としても活動を広げる。現在は株式会社セイボリーの代表を務め、レシピ開発・料理撮影や、調理器具や食品の監修・販促サポートなどの事業を営む。テレビ出演などのメディア実績も多数。著書に「小鍋のレシピ 最新版」(辰巳出版)。









