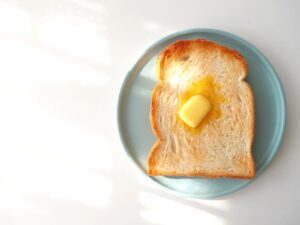
2025.08.23
レシピなしでも味が決まる。調味パーセントを知れば、料理の迷いがなくなる
調理と保存のコツ

「いつもの味」を再現しようとしたのに、なんだか薄い。逆に、気づいたら濃くなりすぎていた──。
レシピを見ないで料理すると、毎回味がブレてしまう。そんな経験、ありませんか。
目分量で調味料を入れていると、その日の気分や疲れ具合で味が変わってしまいます。家族から「今日のは薄いね」「ちょっとしょっぱいかも」と言われると、なんだか自信をなくしてしまいますよね。
実は、プロの料理人や給食の現場では、感覚だけに頼らず「数値」で味を決める方法が使われています。それが「調味パーセント」という考え方です。
一度身につければ、レシピがなくても安定した味付けができるようになります。この記事では、調味パーセントの基本と、今日からすぐに使える計算のコツをお伝えします。
なぜ「1%」がちょうど良いのか
人が「おいしい」と感じる塩味の濃度には、ある程度の共通点があります。それは、およそ0.8〜1.5%の範囲。
この数値が心地よく感じられるのには理由があります。人間の体液の塩分濃度は約0.9%。体になじみやすい濃度だからこそ、「ちょうど良い」と感じるのです。
料理の種類によって、目安となる塩分濃度は少し異なります。
- 汁物やスープ類:0.8%前後
- 主菜やおかず:1.2〜1.5%
- 丼ものやごはんにかける料理:1%前後
汁物は飲み干すことを想定して薄めに。おかずはごはんと一緒に食べるため、やや濃いめに設定されています。
この中で、まず覚えておきたいのが「1%」という数字です。「材料の重さ×1%=必要な塩分量」と覚えておけば、どんな料理でも味付けの出発点が見えてきます。
調味パーセントの計算方法
では、実際にどう計算すればいいのか。2つのステップで見ていきましょう。
まずは材料の重さを合計する
調味パーセントは「材料の重さに対して何%の塩分を加えるか」という考え方です。まず、使う食材の重さをざっくり合計します。
たとえば、豆腐入りハンバーグを作るとしましょう。
- 豚ひき肉:200g
- 木綿豆腐:150g
- 合計:350g
この350gに対して1%の塩分を加えるなら、3.5gが目安になります。
厳密に量る必要はありません。肉のパックに書いてある重さを確認したり、豆腐は1丁あたりの目安(300〜400g)から計算したり。慣れてくると、パッと見で「だいたい300gくらいかな」と見当がつくようになります。
塩分量を調味料に換算する
料理では塩だけでなく、醤油や味噌など、さまざまな調味料を使いますよね。それぞれに含まれる塩分量を知っておくと、換算がスムーズになります。
| 調味料 | 塩分1gに相当する量(ml/g) |
|---|---|
| 食塩 | 0.8(小さじ1/6弱) |
| 醤油 | 5(小さじ1弱) |
| 味噌 | 7(大さじ1/2弱) |
| ウスターソース | 11(小さじ2強) |
| ケチャップ | 30(大さじ2) |
たとえば、肉300g(塩分目安3g)を醤油で味付けするなら、3g×5ml/g=15ml(大さじ1)が適量になります。
計算と聞くと難しそうですが、やっていることはシンプル。「材料の重さ×1%」で塩分量を出し、それを使いたい調味料に換算するだけです。
複数の調味料を組み合わせるときは
実際の料理では、醤油と味噌を両方使ったり、塩と醤油を組み合わせたりすることもありますよね。
その場合は、それぞれの調味料から摂取する塩分を合計して考えます。たとえば、塩分目安が3gの料理で、醤油大さじ1(塩分約2.6g)を使うなら、残り0.4g分を塩少々で補う、という具合です。
最初から完璧に計算しようとしなくて大丈夫。「醤油だけ」「味噌だけ」のシンプルな料理から始めて、慣れてきたら組み合わせに挑戦してみましょう。
感覚をつかむための3つのコツ
計算の仕組みがわかっても、最初から完璧にできる人はいません。ここでは、感覚をつかむためのポイントを3つご紹介します。
1. キッチンスケールで“見える化”する
慣れるまでは、食材の重さや調味料の量をきちんと量ることが大切です。「だいたいこのくらい」ではなく、一度数値で確認することで、自分の感覚と実際のズレに気づけます。
デジタルスケールがあれば、1g単位で量れるので便利です。醤油や味噌を量るときは、容器をスケールに乗せてゼロリセットしてから入れると、汚れずに計量できます。
2. 味見で微調整する習慣をつける
計算で出した塩分量は、あくまで“出発点”です。食材の水分量や、その日の体調によっても感じ方は変わります。
調味料を入れたら、必ず味見をして最終調整を。「もう少し」と思ったら、ほんの少しずつ足していくのがコツです。一度に入れすぎると取り返しがつかなくなりますから。
仕上げの味見を習慣にすると、計算と感覚の両方が育っていきます。
3. 換算表を手の届く場所に貼っておく
塩・醤油・味噌などの換算値は、調理中にさっと確認できると便利です。冷蔵庫の扉やキッチンの壁に貼っておくと、迷ったときにすぐ見られます。
スマホのメモに入れておくのも一つの方法。調理中に手が濡れていることも多いので、すぐ見える場所にあるのが一番です。
塩の種類で味わいが変わることも
調味パーセントを実践するとき、少し注意したいのが塩の種類です。
精製塩はほぼ純粋な塩化ナトリウムなので、塩味がストレートに感じられます。一方、粗塩や天然塩にはミネラルが含まれており、同じグラム数でも塩味がまろやかに感じられることがあります。
最初は精製塩で練習すると、計算どおりの味に仕上がりやすくなります。慣れてきたら、好みの塩に切り替えて微調整を楽しんでみてください。
また、醤油や味噌は商品によって塩分濃度が異なります。減塩タイプを使っている場合は、通常の半分程度の塩分量になっていることも。パッケージの栄養成分表示で食塩相当量を確認しておくと、より正確に計算できます。
調味パーセントが役立つ場面
この考え方を身につけると、こんなときに役立ちます。
- レシピの分量を変えたいとき(2人分を4人分に増やすなど)
- 冷蔵庫にある材料で即興で料理するとき
- 新しい料理に挑戦するとき
「このレシピ、醤油大さじ2って書いてあるけど、肉の量を増やしたら調味料もどれくらい増やせばいいの?」──そんな疑問も、調味パーセントで考えれば解決します。材料の重さに対する割合で考えるので、分量を変えても味がブレにくくなるのです。
1%ルールで、毎日の料理がラクになる
調味パーセントの考え方を知っていると、レシピがなくても味付けに迷わなくなります。
ポイントは2つだけ。
- 材料の重さ×1%で必要な塩分量を出す
- 調味料の換算値を使って、使いたい調味料に置き換える
この2つを押さえておけば、煮物も炒め物も、初めて作る料理でも、ブレない味付けができるようになります。
まずはキッチンスケールを手に、1品から試してみませんか。「なんとなく」ではなく「理論」で味を決める感覚がつかめると、料理がもっと楽しくなるはずです。
ご相談・依頼はこちら
まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
管理栄養士・料理家
ひろのさおり
お茶の水女子大学大学院在学中、フリーランスとして管理栄養士のキャリアをスタート。レシピ開発や執筆業、出張料理サービスに携わり、特定保健指導、セミナー・料理教室講師としても活動を広げる。現在は株式会社セイボリーの代表を務め、レシピ開発・料理撮影や、調理器具や食品の監修・販促サポートなどの事業を営む。テレビ出演などのメディア実績も多数。著書に「小鍋のレシピ 最新版」(辰巳出版)。









