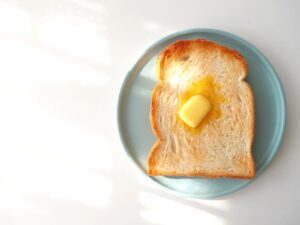
2025.07.18
家庭でできる食中毒予防と抗菌食材の活かし方
調理と保存のコツ

朝、お弁当箱に詰めたおかずを眺めて「この暑さで傷まないかな」と不安になる。冷蔵庫から作り置きを取り出すとき「そういえば、いつ作ったっけ」と首をかしげる。梅雨から夏にかけて、そんな瞬間が増えていませんか。
気温と湿度が上がるこの季節は、細菌が活発に増えやすい時期。でも実は、毎日のちょっとした工夫で食中毒のリスクはぐっと減らせます。
ここでは、予防の基本から、昔ながらの知恵を活かした抗菌食材の使い方まで、家庭で無理なく続けられる対策をご紹介します。
食中毒はなぜ起きるのか
食中毒の多くは、細菌やウイルスが食べ物に付着し、増殖したものを口にすることで起こります。
特に気をつけたいのが10〜50℃の温度帯です。この範囲は細菌にとって居心地のよい環境。調理後の料理を室温に置きっぱなしにしたり、冷蔵庫にものを詰め込みすぎて冷えが悪くなったり。何気ない日常の習慣が、菌の増殖を後押ししてしまうことがあります。
また、調理中に生肉や生魚を触った手でそのまま野菜を切る、といった動作も要注意。目に見えない菌が、気づかないうちに広がっていきます。
予防の基本は、菌を付けない・菌を増やさない・菌をやっつけるの3つ。この原則を押さえておくだけで、家庭での食中毒リスクは大きく減らせます。
まずは菌を持ち込まない・広げない
食中毒対策の第一歩は「菌を付けない」こと。調理の現場に菌を持ち込まず、食材同士で広げないことが大切です。
手洗いは30秒を目安に
調理前、生肉や生魚を触った後、盛り付け前。この3つのタイミングで手を洗う習慣をつけましょう。流水でさっと流すだけでは不十分です。石けんを使い、指の間や爪の周りまで丁寧に。目安は30秒ほど。「ハッピーバースデー」を2回歌い切るくらいの長さです。
まな板と包丁は使い分ける
肉・魚用と野菜用で、まな板や包丁を分けるのが理想的です。難しければ、肉や魚を切った後にすぐ洗剤で洗い、熱湯をかけてから野菜を切るようにしましょう。菌の「引っ越し」を防ぐことがポイントです。
素手で触らない工夫
おにぎりやサンドイッチなど、直接手で触れる料理は要注意。ラップや使い捨て手袋を活用すれば、手から食品への菌の移動を防げます。特にお弁当に入れるものは、この一手間が安心につながります。
温度管理と水分コントロールで菌を増やさない
付いてしまった菌を増やさないためには、温度と水分の管理がカギになります。
調理後は素早く冷ます
カレーや煮物など、大量に作った料理をそのまま鍋に入れておくと、中心部がなかなか冷めません。菌にとっては絶好の増殖タイムです。
おすすめは、浅い容器に移し替えてうちわであおぐ方法。表面積を広げて熱を逃がすことで、素早く粗熱を取れます。冷めたら早めに冷蔵庫へ。
冷蔵庫は7割収納を目安に
冷蔵庫にものを詰め込みすぎると、冷気の循環が悪くなり、庫内温度が上がってしまいます。目安は7割程度の収納率。月に一度は温度計でチェックし、4℃以下を保てているか確認しましょう。
水分の多い料理はひと工夫
水分が多いと菌が繁殖しやすくなります。お弁当のおかずは、汁気をしっかり切ってから詰めるのが基本。煮物は少し濃いめの味付けにする、炒め物に片栗粉でとろみを付けるなど、水分をコントロールする工夫も有効です。
加熱と殺菌で菌をやっつける
付けない・増やさないを徹底しても、完全に菌をゼロにするのは難しいもの。最後の砦となるのが「加熱」です。
中心温度75℃で1分以上を目安に
特に注意したいのが鶏肉やひき肉。中までしっかり火が通っているか、切って確認する習慣をつけましょう。中心部がピンク色のままだと、菌が生き残っている可能性があります。
目安は中心温度75℃で1分以上。料理用温度計があると確実ですが、なくても「肉汁が透明になるまで」を判断基準にできます。
調理器具は使用後すぐに熱湯を
まな板や包丁は、使い終わったらすぐに洗剤で洗い、熱湯を回しかけます。菌は熱に弱いため、この一手間で衛生状態がぐっと変わります。
ふきんやスポンジも見落としがちなポイント。毎日しっかり洗って乾燥させ、週に一度は漂白剤で殺菌するのがおすすめです。湿ったまま放置すると、菌の温床になってしまいます。
台所でできる小さな習慣
特別な道具や大きな手間は必要ありません。毎日の食事作りの中で、ちょっとした習慣をプラスするだけで、食中毒のリスクは下げられます。
手洗いのタイミングを「調理前・生もの後・盛り付け前」の3回に固定してしまえば、考えなくても体が動くようになります。冷蔵庫は週に一度、中身を整理するついでに拭き掃除を。期限切れの食材をなくし、衛生状態も保てます。
お弁当を作るときは、水分控えめのおかずを選び、酢や塩を効かせた味付けを意識してみてください。梅干しを混ぜ込んだご飯や、酢の物を一品添えるだけでも違います。
抗菌食材を味方につける
古くから日本の食卓で使われてきた食材の中には、抗菌作用を持つものがあります。予防の3原則に加えて、こうした食材を日々の料理に取り入れることで、保存性と風味を同時に高められます。
梅干しのクエン酸
梅干しに含まれるクエン酸には、菌の増殖を抑える働きがあります。お弁当のご飯に混ぜ込んだり、刻んでおかずに添えたり。昔ながらの「日の丸弁当」には、ちゃんと理由があったのです。
選ぶなら、塩分10%以上のものが防腐効果は高め。減塩タイプは食べやすい反面、保存目的には向きません。
大葉のペリルアルデヒド
大葉の独特な香りのもとであるペリルアルデヒドには、抗菌作用があります。刻んでご飯に混ぜる、肉や魚に巻いて焼くなど、使い方は自由自在。お弁当の仕切りに使えば、見た目も鮮やかになります。
わさびとしょうがの辛み成分
わさびに含まれるアリルイソチオシアネート、しょうがに含まれるジンゲロールも、抗菌作用が知られています。わさびはドレッシングやおにぎりの具に、しょうがは漬け込みや炒め物に。風味を楽しみながら、さりげなく食中毒対策ができます。
スパイスと柑橘の力
カレー粉に使われる複合スパイスにも、抗菌効果が期待できます。保存おかずの味付けに使えば、独特の風味で飽きにくく、日持ちも良くなります。
レモンのクエン酸は、マリネや下味に活用を。果汁を後からかけるより、漬け込んで使うほうが効果が持続します。
抗菌食材を使うときのポイント
こうした食材は“魔法のアイテム”ではありません。あくまで予防の3原則を実践した上で、補助的に活用するものと考えてください。
スパイス類は開封後、湿気を避けて半年以内に使い切るのが目安。古くなると香りも抗菌効果も弱まります。
食の安全は小さな積み重ねから
食中毒対策は「菌を付けない・増やさない・やっつける」の3原則が基本。そこに抗菌食材を上手に組み合わせれば、毎日の食事はもっと安全になります。
特別なことをする必要はありません。手洗いのタイミングを決める、冷蔵庫の温度を確認する、お弁当に梅干しを一粒添える。そんな小さな習慣の積み重ねが、大切な人の健康を守ります。
今日から台所でできる工夫を、ひとつ取り入れてみませんか。
ご相談・依頼はこちら
まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
管理栄養士・料理家
ひろのさおり
お茶の水女子大学大学院在学中、フリーランスとして管理栄養士のキャリアをスタート。レシピ開発や執筆業、出張料理サービスに携わり、特定保健指導、セミナー・料理教室講師としても活動を広げる。現在は株式会社セイボリーの代表を務め、レシピ開発・料理撮影や、調理器具や食品の監修・販促サポートなどの事業を営む。テレビ出演などのメディア実績も多数。著書に「小鍋のレシピ 最新版」(辰巳出版)。









